- すべてが桁違い!動物たちのさまざまなNO.1を楽しく学ぼう
- 野生動物よりも人間が優れている能力は、実は〇〇力!
- 能力を得るに至った、動物たちのライフスタイルや生息環境も調べてみよう

今回は、動物界の『NO.1』を一挙に紹介!足の速さやジャンプ力・大きさや小ささなど、地球上の動物たちの第1位を発表していきます。野生動物たちの底知れぬパワーを、豆知識と一緒に楽しみながら学んでいきましょう!
【体力・パワー編】動物界のNO.1 6選
まずは、身体能力に関連するNO.1を紹介していきます。人間は素手では到底敵わない、圧倒的な野生動物たちの身体。生存戦略に基づいたエネルギッシュな身体能力にふれていきましょう。
チーター|足の速さNO.1

世界一足が速い生き物は、アフリカのサバンナに生息するチーター!チーターは最高時速110kmで走ります。この速度は、高速道路を走る車よりも速いのだとか。
人類史上最速とされるウサイン・ボルトの最高時速は、約44.7km。ボルト選手の倍以上速いチーターに狙われたら、人間はひとたまりもありません!
人間|持久力NO.1

動物界でもっとも持久力が高いといわれているのは、なんと人間なんです。ただし10km程度の中距離の移動であれば、瞬発力や速度の面でオオカミやウマに軍配が上がります。
しかしフルマラソンのような長距離であれば、人間はあらゆる野生動物を超えるといわれています。人間は汗による体温調節機能が高く、二足歩行によって効率的なエネルギー消費ができることから、非常に優れた持久力を持つ生き物なのです。
ピューマ|ジャンプ力NO.1

ジャンプ力NO.1の生き物は、南北アメリカ大陸に生息するネコ科のピューマ。体長は1~2m程度ですが、ジャンプする高さはなんと約7m!
建物の2階程度であれば、簡単にジャンプできる脚力を持っているんです。ただし『身長の何倍ジャンプできるか』という観点であれば、ノミ(昆虫)の160倍が圧倒的な数値です。
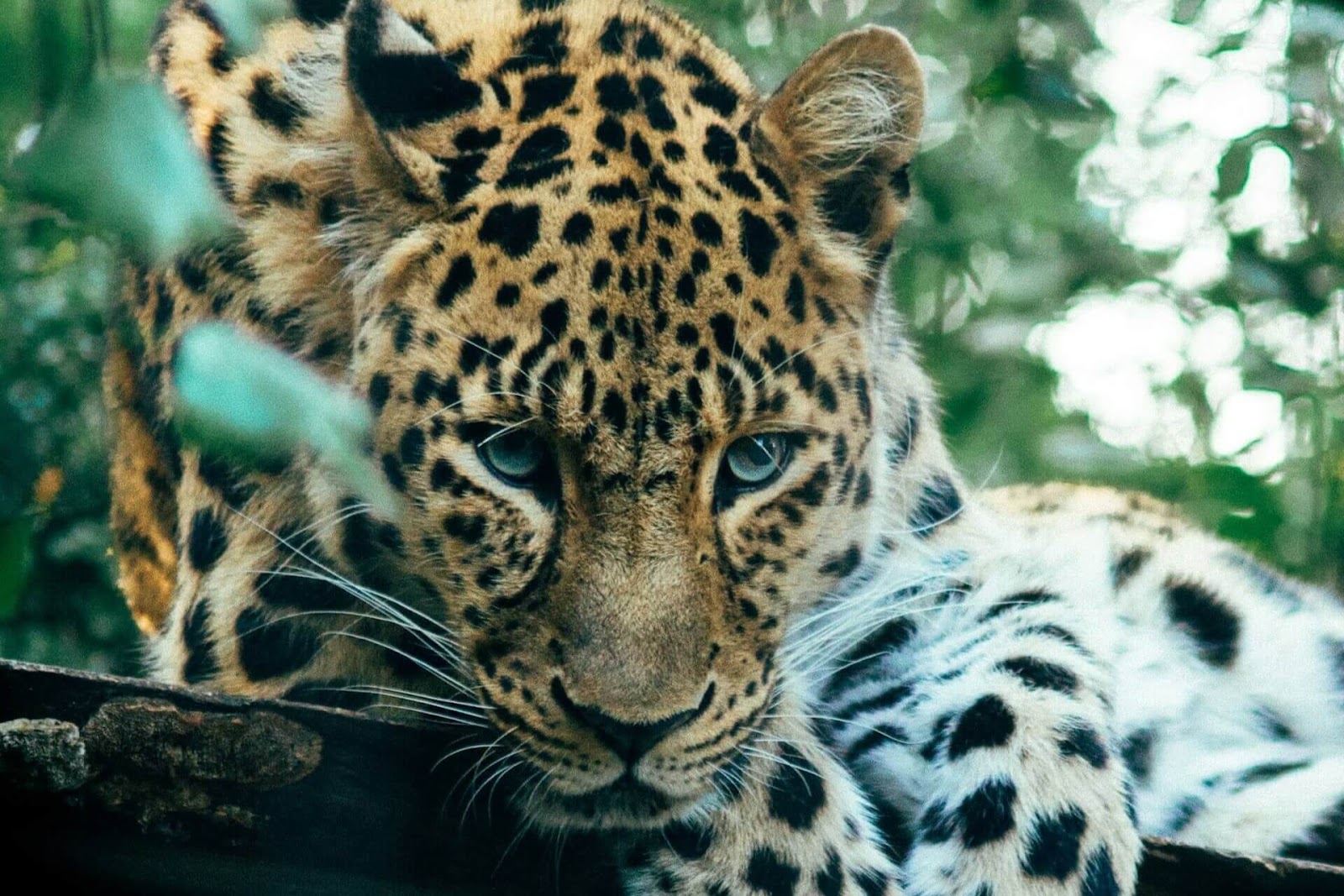
ダチョウ|キック力・視力 NO.1

5tに迫る圧倒的なキック力
世界でもっともキック力が強い生き物は、世界最大の鳥であるダチョウです。ダチョウは飛行能力がない代わりに、驚くべき身体能力を持っています。
時速70kmで走る脚力もさることながら、その強靭な脚力を活かしたキックは殺人級。100㎠あたり5t弱の圧力を与えられるとされ、過去には男性がダチョウに蹴られ、頭蓋骨を砕かれて亡くなってしまった事故も起きています。
アリの動きを補足できる視力
ダチョウの身体能力の高さは脚力だけではありません。実はダチョウは非常に視力が高い生き物。人間の視力の平均値は約0.5といわれていますが、ダチョウはなんと20!
この視力は、40m以上先を歩いているアリの動きがよく分かるほどの高さといわれています。人間には想像すらできないほどの世界ですよね。ダチョウは高い視力を活用して、チーターやライオンなどの捕食者から身を守っています。
イリエワニ|咬む力NO.1

咬む力は『咬合力』の数値で表せます。参考までに、人間の咬合力は最大約70kg程度です。そして動物界最強の咬合力を持つのは、アジア大陸やオーストラリアに生息するイリエワニ。イリエワニの咬合力は、人間の45倍を超える3,185kgといわれています。
咬合力で2位のカバが約745kgであることから、まさに圧倒的なパワーを持っていることがわかります。ただしイリエワニは『口を開く力』は非常に弱く、テープを2〜3周巻くだけでも口を開けなくなってしまうのだとか。
ハリオアマツバメ|飛行力NO.1

ギネスブックでは『世界一速い鳥』としてハリオアマツバメが記録されています。ハリオアマツバメは、日本を含む世界各地に生息するツバメの一種。水平飛行時の速さは、チーターも相手にならない時速170km!
日本人で最高速度のボールを投げた野球投手は、大谷翔平選手の165km。トッププロの投球よりも速い速度で飛ぶハリオアマツバメは、生活の大半を飛びながら過ごし、なんと睡眠や交尾すらも飛行中なのだとか。
【頭脳編】動物界のNO.1 2選
ここでは、頭脳に関する動物界のナンバーワンを紹介します!人間が野生動物に勝てる、ほぼ唯一の武器が知能。しかし一部の動物たちは、人間が恐れを抱くほどの高い知能を所持しています。
チンパンジー|IQの高さNO.1

チンパンジーのDNAは、約99%が人間と合致しています。遺伝子上は『ほぼ人間』と言っても過言ではない生き物です。動物界のなかでもトップの知能を持っていることにも頷けます。
道具の利用や、手話を利用したコミュニケーションも可能なチンパンジー。高度な共同体を形成する社会性も持っており、自己認識や感情の理解が可能であることも判明しています。
イルカ|記憶力NO.1

高い知能を持つ生き物として有名なイルカですが、特筆すべきはその記憶力です。イルカは20年前に会ったことがある仲間を認識できるほど、動物界トップの長期記憶能力を持っています。
過去には、イルカにさまざまなホイッスル音(イルカがコミュニケーションで使う音)を聞かせる実験を実施。その結果、無作為に選んだ音よりも『数十年前に群れにいた個体の音』に顕著に反応したという記録が残っています。
【生活力編】動物界のNO.1 4選
ここでは、生活力に由来する動物界のNO.1を紹介します。生存戦略のために必要なのは、その環境に適した特性や武器。動物ごとに進化した独自性の高い特徴を学び、ミステリアスな生き物の世界にふれてみましょう。
アルダブラゾウカメ|寿命の長さNO.1

世界でもっとも寿命が長い生き物は、ゾウガメの一種であるアルダブラゾウガメといわれています。アルダブラゾウガメの平均寿命は、約200歳。過去の飼育記録では255歳まで生きたデータが残っています。
あまりにも長寿であることから、死因の過半数は老衰ではなく『熱中症』なのだとか。アルダブラゾウガメ以外でも、大型のカメ類は非常に寿命が長い生き物として知られます。

ズグロモリモズ|毒の強さNO.1

動物のなかには、自己防衛や捕食のために、強い毒を駆使する種類も少なくありません。陸上でもっとも強い毒を持つのは、インドネシアやパプアニューギニアなどに生息する鳥、ズグロモリモズです。
見た目はただの可愛い小鳥という印象ですが、ズグロモリモズの毒は青酸カリの5,000倍という凶悪さ。羽には『バトラコトキシン』という猛毒が含まれており、人間であれば羽1枚分の毒量で死んでしまいます。
シロナガスクジラ|食いしん坊NO.1

世界でもっとも食べる量が多い生き物は、地球上の広い海域に生息するシロナガスクジラです。クジラの主食は動物プランクトンやオキアミなど。大きな口を開け、海水からこし取るようなかたちで食べています。
1日に食べる餌の量は、平均16t。打ち上げられたクジラを解剖すると、まるで漁を終えた漁船のように大量の小魚が出てきます。そして食べる量と比例して『出す量』が多いのもシロナガスクジラの特徴。クジラの排泄物は海の生態系に対し、重要な栄養素を供給していると考えられています。
コアラ|睡眠時間NO.1

世界でもっとも睡眠時間が長い動物は、コアラです。コアラの1日の睡眠時間は、約18~22時間。1日の大半を眠りながら過ごしています。
この背景には、コアラの主食であるユーカリの葉が関連しています。ユーカリの葉には強い毒性が含まれており、消化には多大なエネルギーが必要です。不必要なエネルギー消費を抑えるために、眠ることによって『省エネ』をしているのです。
【大きさ・多さ編】動物界のNO.1 3選
ここでは、大きさや多さに関連するNO.1を紹介します。動物たちの生態を知るほど、その多様性に圧倒される気持ちになりますよね。普段はなかなか出会うことのない『大きい・小さい・多い』生き物たちを学んでみましょう。
シロナガスクジラ|大きさNO.1

動物が1日で食べる量は、基本的に身体の大きさに比例します。世界一食べる量が多い動物であるシロナガスクジラは、文句なしの『地球上でもっとも大きい動物』です。
シロナガスクジラは、現存する動物種だけではなく、かつて地球に存在したすべての生命を含めても、最大の種類と考えられています。
確認されている最大個体の大きさは、体長30.5m!これは一般的なマンションの10階建て程度のサイズ感です。あまりにも規模が大きすぎて、クラクラしてきます……!
コビトジャコウネズミ|小ささNO.1
現存する生き物のなかで、もっとも小さい動物はコビトジャコウネズミです。体長は約3cm(+尾)、体重は約2g。手のひらに乗せても気づかないほどの軽さです。平均的なネズミよりも、約20倍以上軽いといわれています。
その小ささから温度変化に非常に敏感であり、体温を一定に保つためには大量のエネルギーが必要になります。そのためコビトジャコウネズミは代謝率がとても高く、心拍数は1秒あたり14回という多さです。
オキアミ|生息数の多さNO.1

地球でもっとも生息数が多い生き物は、世界最大のプランクトンであるオキアミです。その圧倒的な総量から『生物界の主役』とも呼ばれます。
世界中で85種類が分布しているオキアミ。あまりにも膨大な数が住んでいるため、測定は『匹数』ではなく『重量』でおこなわれます。その推定総量は、なんと5億t!オキアミ1匹が約2g程度なので、計算すると……頭が痛くなってきました!
とくに個体数が多いとされるナンキョクオキアミだけでも、詳細な測定は難しいものの、世界中に600兆匹以上は生息していると考えられています。
人間には到底かなわない、動物たちの神秘の世界!

今回は、動物界のさまざまなNO.1を紹介しました。
動物たちの底知れぬパワーの背景には、生息地特有の環境や、ほかの生き物との関係性も影響しています。ぜひ本記事をきっかけに、各動物の詳しいライフスタイルも調べてみてください!













