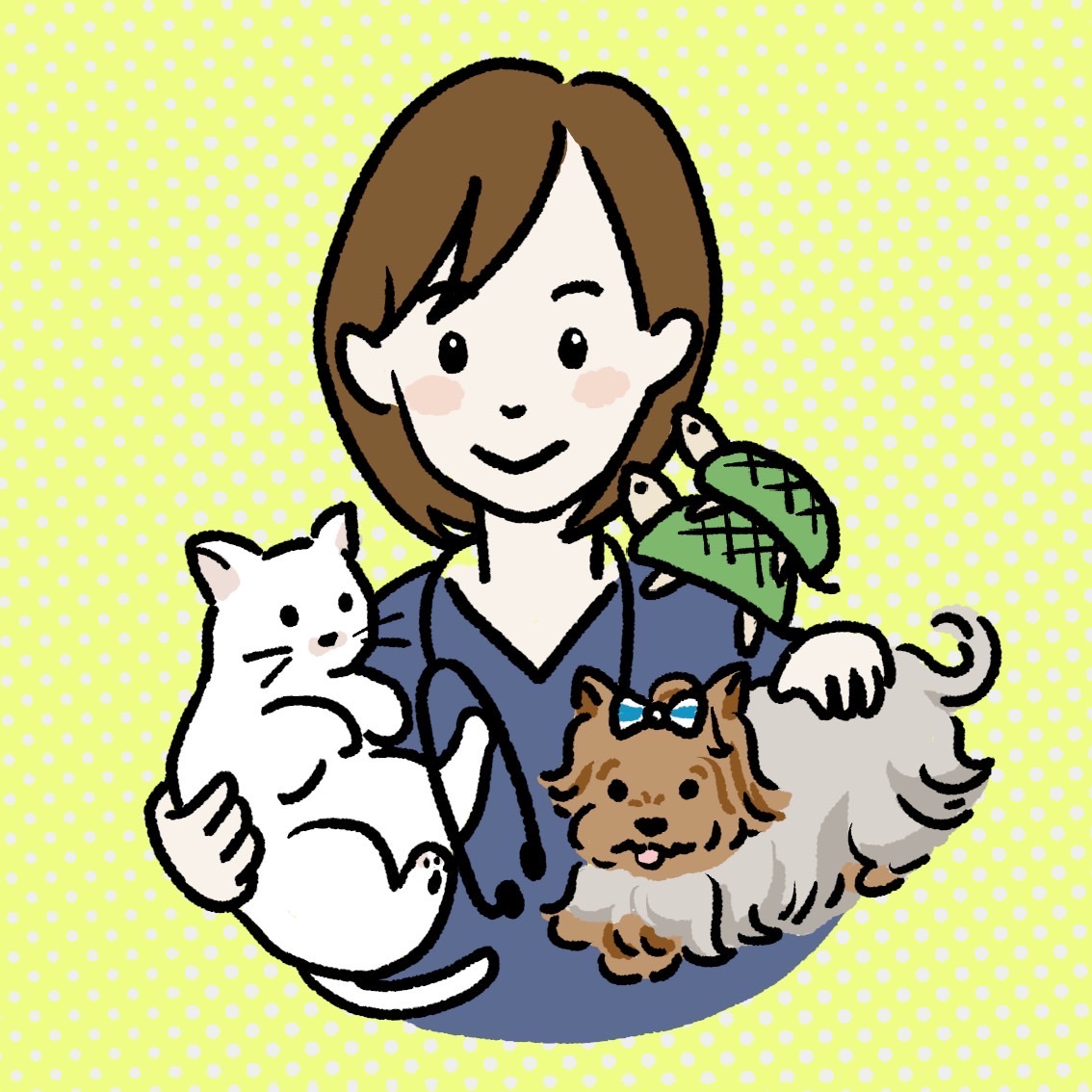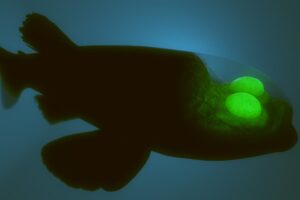- オタリアは『鰭脚類(ききゃくるい)』の一種
- 力強い鳴き声や、オスのたてがみから『SeaLion』と呼ばれる
- アシカにそっくりだが、耳たぶと鼻を観察すれば見分けられる!
- 海の哺乳類であるオタリア飼育にはたくさんの工夫が必要

オタリアという動物を知っていますか?名前も聞いたことがない、という人も多いかもしれません。オタリアは、海に住む哺乳類の一種です。見た目がアシカに似ているため、ほとんどの人がオタリアを見ても「アシカがいる!」と思うでしょう。
今回は、オタリアの飼育施設で働く筆者が、読者に「オタリアを見に行きたい!」と思ってもらうことを目標に、オタリアを含めた海の哺乳類についての解説や、オタリアの生態を解説します。

カイジュウ?ヒレアシ?海の哺乳類の呼び名と分類

イルカやアシカは、哺乳類でありながら海で生活する動物です。ここでは、オタリアを含む海の哺乳類についての概要をお伝えします。
海に住む哺乳類の総称が海獣(カイジュウ)
水族館の職員から「カイジュウを担当しています」と聞くと、ついゴジラを思い浮かべてしまいますね。
しかし、ここでのカイジュウは『怪獣』のことではありません。 動物園や水族館では、イルカやアシカ・オットセイなど、海に住む哺乳類の総称が『海獣(カイジュウ)』です。
海獣は、哺乳類でありながら、海での生活に適応できるように進化した動物です。
海獣という言葉は、分類学的に正式なものではなく、イルカやアシカなどの他に、ホッキョクグマやラッコを含むこともありますが、一般的には、鯨類(げいるい)・海牛類(かいぎゅうるい)・鰭脚類(ききゃくるい)の3種を指すことが多いと言えます。
鯨類(げいるい)・海牛類(かいぎゅうるい)・鰭脚類(ききゃくるい)をそれぞれ解説
海獣は大きく『鯨類(げいるい)』『海牛類(かいぎゅうるい)』『鰭脚類(ききゃくるい)』の3種に分けられます。鯨類は、その名の通りクジラの仲間です。魚のように胸ビレがあり、後ろ足は進化の過程でなくなりました。
皆さんがよく水族館で出会うイルカも、分類学的にはクジラで、体長4mを超えるものをクジラ、それより小さいものをイルカと呼びます。
海牛類とは、ジュゴンやマナティーです。鯨類と同様に、完全な水中生活を送ります。前足はヒレ状で後ろ足は退化しています。海牛類は、肉食動物の鯨類とは異なり、海藻や水草などを食べる草食動物です。
今回紹介するオタリアは『鰭脚類』の一種です。『ききゃくるい』と呼ぶのが学術的には正しいですが、動物園や水族館では『ヒレアシ類』や単に『ヒレアシ』とも呼びます。
鯨類や海牛類とは異なり、四肢があります。四肢はヒレ状で、水中での暮らしにも有利ですが、陸上でも生活を行います。鯨類や海牛類と比較すると、一番哺乳類であることがわかりやすいかもしれません。
優雅に泳ぐ鯨類(イルカ)

ヒレ状の前足を器用に使う海牛類(マナティー)

陸上でも生活する鰭脚類(アシカ)

オタリアの基礎知識。アシカとの違いを知ろう。

ここではオタリアの分類や生息地などの基本情報に加えて、見た目がそっくりなアシカとの見分け方を紹介します。
生息地は南米の海。オスにはライオンのようなたてがみがあるのが特徴。

オタリアは、学名をOtaria flavescens、英語名をSouthAmericanSeaLionと言います。アシカ科のオタリア属に属する動物で、チリなどの南アメリカの太平洋・大西洋の沿岸に生息しています。
野生下のオタリアは通常、さまざまな小魚・イカ・タコなどの生きものを捕まえて食べます。潜水が得意で、獲物を追う時は水が鼻から入らないように鼻の孔を意識的に閉じることができます。
水中では前ヒレを使って羽ばたくように自由自在に泳ぎ、後ろ足はぴたりとそろえて舵の役割をし、時にはイルカのようにジャンプをすることもあります。
長いひげは、センサーの役割を果たす大切な器官です。飼育下のオタリアの場合、ひげの長さや巻き方がこの個体を見分ける特徴にもなります。
四肢はヒレ状ですが、指があり、四肢の先まで器用に使うことができます。例えば、岩場の隙間に指(ヒレ)をひっかけてよじ登るという行動もできるのです。
オタリアの鳴き声は力強く「ガオ―」と遠吠えするような鳴き方をすることもあれば「ガオガオ」と語りかけるような声を出すこともできます。
オスとメスでは体格や見た目に大きな違いがあり、メスの体の大きさは1.5~2m程度、体重は成長しても100Kg~170kg程度ですが、オス2~2.6m、350kgにも達します。また、オスにはライオンのようなたてがみ状の毛があり、この姿と、ライオンのような鳴き声がSeaLionという名前の由来です。
アシカとの見分け方は耳たぶと鼻
オタリアはアシカ科の動物で、アシカとそっくりです。
オスの場合は、たてがみの有り無しで簡単に見分けられます。オタリアのオスにはたてがみがありますが、アシカのオスにはありません。
たてがみで見分けられないメスの場合、少し観察力が必要です。ポイントは、耳たぶと鼻で、アシカに比べてオタリアの耳たぶは小さく、鼻が短くて大きいです。アシカの顔をシュッとしているとするなら、オタリアは少しだけ鼻ぺちゃで『ぶさかわ』だと言えるかもしれません。
耳たぶがかわいいアシカの顔

鼻が特徴的なオタリアの顔(オス)

オタリアの魅力や飼育の工夫を紹介

オタリアは好奇心旺盛で、自分たちを観察している人間を反対に観察しているような面もあります。ここではオタリアの魅力や飼育施設での工夫について紹介します。
オタリアは好奇心旺盛、ややおっとりな面も
どんな動物でも、個体ごとに性格は異なりますが、オタリアの多くは非常に好奇心が旺盛です。水族館や動物園のオタリアたちは、お客さんのことをよく見ていて、お客さんが持っているものにも興味津々です。
アシカも同じように好奇心旺盛な動物ですが、アシカよりも少しおっとりしている個体が多いというのも、関係者のあいだでよく言われています。陽気さが全面に出るアシカよりも、慎重さが勝つ個体が多い印象です。
新しいおもちゃをもらうと、すぐに飛びついて遊んでみる個体が多いのがアシカで、オタリアの場合はしばらく横目でじっと見ながら周囲を泳ぎ、安全であることを確認してから遊びはじめる個体が多いです。
人の顔もよく見分け、はじめての人が近づくと警戒する一方で、好きな職員を見つけると、大急ぎで寄って行きます。体を動かして遊ぶのも好きで、手を振ったり、逆立ちをするなど、トレーナーと息のあったパフォーマンスを見せてくれることもあります。
海の生き物であるオタリア飼育のための工夫とは
オタリアはもともと海の動物なので、海水で飼育するのが望ましいです。しかし、施設の立地によっては海水利用のハードルが高く、真水を使用することも少なくありません。そのため、塩分不足にならないように、餌に塩を添加する必要があります。
また広い海とは異なり、人工的なプールの水質はすぐに悪化してしまいます。水質悪化は皮膚病や目のトラブルにつながるため、各施設ではろ過機の使用はもちろん、こまめなプール掃除と水の交換が欠かせません。
飼育の苦労は施設の面だけではありません。
好奇心いっぱいのオタリアは、飼育下での単調な生活にストレスを感じやすい動物です。トレーニングの種目に変化をつける、新しいおもちゃを与えるなど、常に良い刺激を与える工夫も必要です。飼育員たちは、少しでもオタリアが楽しい生活を送れるように日々知恵を絞っているのです。
会いに行ける!オタリアのいる水族館・動物園

ここではオタリアに会える水族館・動物園を紹介します。ぜひ泳いだり遊んだりするオタリアの様子を間近で見てみてください。
8月に赤ちゃんが産まれたばかり!オタリアは成熟するまでに5〜10年といわれています。今しか見られない赤ちゃんの様子を見にいきましょう。
関東付近でオタリアを見るならおすすめの水族館です。
8月に八景島シーパラダイスで赤ちゃんを産んだ『ヤヨイ』も、もともとはここの水族館で暮らしていて繁殖のためにシーパラダイスに移動しました。
フレンドリータイムと言って、オタリアと写真を撮ったり背中にタッチさせてもらえるイベントがあります。(有料で¥1.000)観光客にも大人気でいつも人がいっぱいです。
日本で唯一ジュゴンもみることができます。今回の記事で紹介した、3種の海獣すべてがみられます。
メスの『ちゅら』と『きらり』が仲良く暮らしています。無料で入れるのでふらりと立ち寄ってオタリアに会うことができます。
秋の行楽シーズンにはオタリアに会いに行こう

今回は、あまり知られることのない海の哺乳類、オタリアを紹介しました。日本でオタリアを飼育している施設はそれほど多くありませんが、秋の行楽シーズンには是非水族館や動物園に出かけてオタリアを観察してみてください。
アシカとの区別がつくようになったら、ちょっとした海獣博士ですね。