- 妊娠・出産時の猫のお世話は、1人で無理をせずに周りを頼ろう
- 猫から妊婦さんにうつる感染症を知り、具体的な対策につなげよう
- 人間側に余裕がなくなりやすい時期だからこそ、家族とお世話について事前に話し合うことが大切

妊娠・出産におけるライフスタイルの変化は、愛猫との暮らしにも影響を与えます。今回は、妊婦さんや赤ちゃんが猫と暮らす際に注意したいポイントを紹介します。人も猫も安全に生活するために、適切な環境や関わり方について考えていきましょう。
監修者
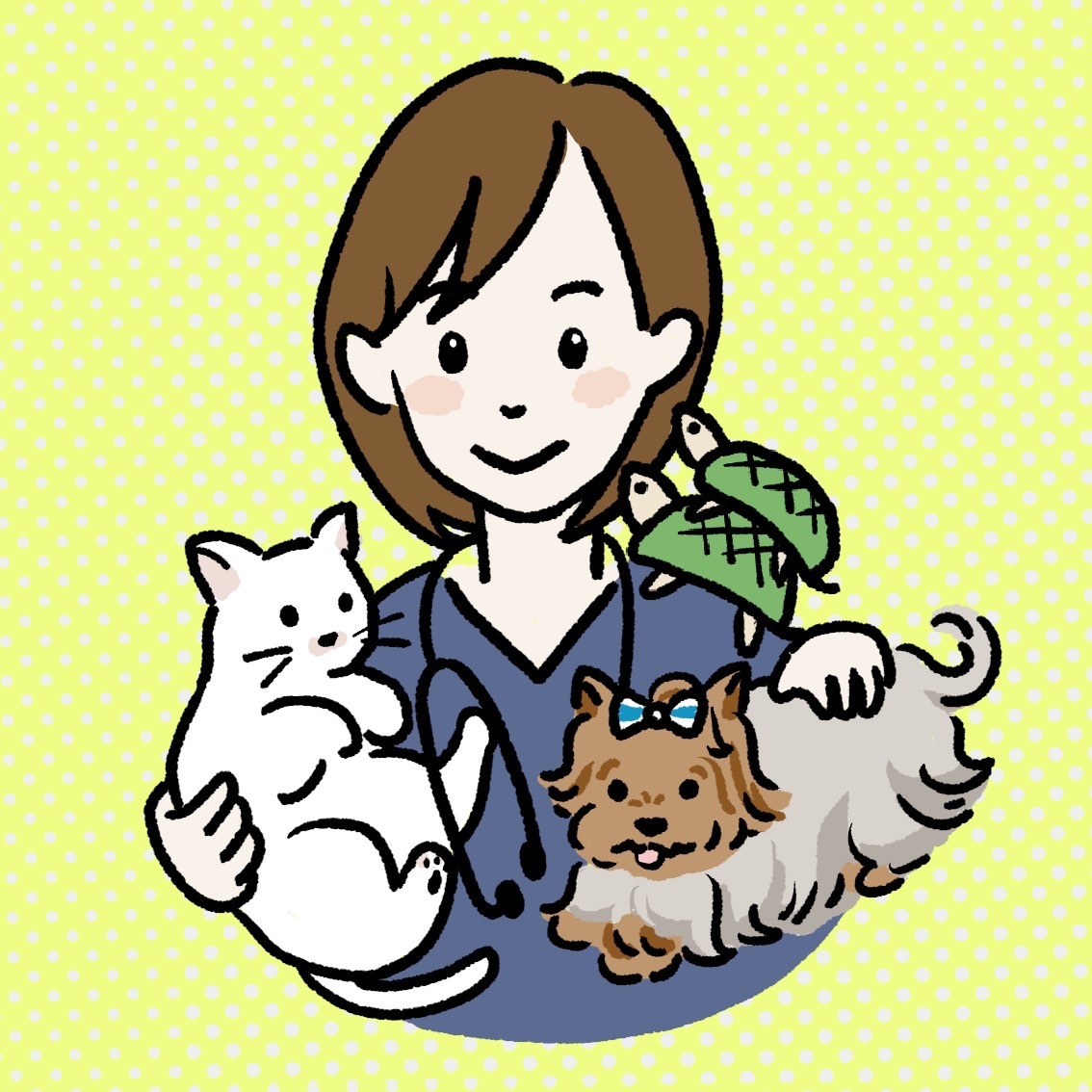
ttm 医師
岩手大学で動物の病態診断学を学び、獣医師として7年の実績があり、動物園獣医師として活躍中。動物の病態に精通し、対応可能動物は多岐にわたる。
妊婦が注意するべき、猫の『人獣共通感染症』

ここでは、妊婦さんが注意したい猫の『人獣共通感染症』を紹介します。人獣共通感染症とは、人間と動物の両方にうつる感染症のこと。妊婦さんの体にも影響を与える感染症を学び、愛猫とのライフスタイルをより安心なものにしていきましょう。
トキソプラズマ症
猫の人獣共通感染症で、もっとも注意したいのがトキソプラズマ症。猫の便から感染するリスクがあり、妊婦が感染すると胎盤を通じて胎児にも感染してしまいます。
胎児への感染率は10~70%といわれており、妊娠初期に感染するほど重症度が高い傾向に。胎児の流死産の可能性もある恐ろしい感染症です。出産後も、視力障害などの病気を発症するケースがあります。
ただし、猫を飼っているからと言って、過度に恐れる必要はありません。
猫の便に潜むトキソプラズマの感染体であるオーシストは、便と共に下界に出ても、すぐに感染の能力を持つわけではありません。感染能力を得るためには、24時間程度の時間が必要なので、すぐに便を処理すれば大きな心配はないのです。
参考:JAMC「猫と妊婦さんの重要な感染症~トキソプラズマ症~」
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)
重症熱性血小板減少症候群は、ウイルスを持つマダニに刺されることや、SFTSを発症している動物と接触することで感染する人獣共通感染症です。最大2週間程度の潜伏期の後、発熱・腹痛・消化器症状などが現れ、致死率も高い(10~30%)病気です。
直接マダニに刺されなくても、飼っている犬や猫が感染した場合、飼主が感染する可能性があります。
対症療法として抗ウイルス剤『ファビピラビル』が用いられますが、動物実験によって初期胚の致死や催奇形性が報告されているため、妊婦には禁忌となるため使用できません。
完全に室内飼いの猫の場合、大きな心配はありませんが、外に自由に出ることができる猫は、感染のリスクがあるため注意が必要です。
参考:厚生労働省「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)について」
ネコひっかき病(バルトネラ症)
ネコひっかき病は、感染した猫に引っかかれたり咬まれたりすることで感染する病気です。猫は感染しても無症状ですが、人だけが発症します。
最初は傷が赤く腫れるだけですが、次第に発熱や頭痛・リンパ節の腫れなどの症状が現れます。
一般的なネコひっかき病は自然治癒されますが、妊娠中のように免疫機能が下がりやすい状態では、感染が全身に広がる可能性も。症状を放置すると、最悪の場合は命の危険もあります。
コリネバクテリウム・ウルセランス感染症
コリネバクテリウム・ウルセランス感染症(省略されて『ウルセランス感染症』とだけ呼ばれる場合もあります)は、感染した猫の飛沫から感染する可能性がある感染症です。
猫の症状はくしゃみ・鼻水・皮膚疾患などですが、人間の場合はさらに咳や扁桃・咽頭の異常などが現れます。国内での感染報告は稀なものの、重篤な症状の場合には呼吸困難になり、命にかかわる場合もあります。
参考:厚生労働省「コリネバクテリウム・ウルセランスに関するQ&A」
パスツレラ症
パスツレラ症は、猫に咬まれたり引っかかれたりすることで細菌に感染してしまう病気です。感染すると腫れや痛みが生じた後、急激に炎症が拡大していきます。重篤な症状だと敗血症に進行することもある、恐ろしい感染症です。
パスツレラ属菌は、猫の口腔内にほぼ100%常在している菌です。そのためペットとのキスや口移しなどでも感染するリスクがあり、皮膚だけではなく呼吸器系が感染してしまうこともあります。
皮膚糸状菌症
皮膚糸状菌症は、感染した猫との接触によって感染する皮膚病です。猫や人が発症すると、発症した皮膚にリングワームと呼ばれる特徴的な円形の脱毛がみられます。猫では脱毛以外にも、皮膚の赤み、フケの発生などさまざまな症状が現れます。妊婦さんにはもちろん、生まれたばかりの赤ちゃんにも感染してしまう病気です。
治療に用いられることのあるステロイドは、妊婦さんへの利用に制限を設けられる場合があります。
参考:MSDマニュアル家庭版「皮膚糸状菌症(白癬、たむし)の概要」
参考:湯川リウマチ内科クリニック「妊娠・出産時の関節リウマチの薬」
妊婦や赤ちゃんが猫と暮らすときのポイント・注意点

ここでは、妊婦さんや赤ちゃんが猫と暮らすときのポイントを紹介します。妊娠中だけではなく、出産後の暮らしでも注意点は多いもの。人の体のケアと猫の心のケアを両立できるように、家族の協力も得ながら理想的なライフスタイルを考えていきましょう。
ノミやダニ・マダニの対策
猫との暮らしでは、人獣共通感染症を予防するためにもノミやダニ・マダニの対策が必須。ノミ・ダニは、乳児へのアレルギー反応を誘発する場合もあります。
室内飼育の猫でも、動物病院への移動や荷物の持ち込みなどがきっかけで、ノミやダニに寄生されてしまうことも。スポットタイプのクスリや飲み薬などを併用し、獣医師と相談しながら適切な方法で対策しましょう。
お外に自由に出ることができる猫では、マダニ対策も欠かせません。
完全室内飼育を徹底する
もし猫を室外飼育・半室外飼育している場合は、妊娠中の段階から完全室内飼育を徹底してください。完全室内飼育はノミ・マダニの寄生だけではなく、野良猫や排泄物からの感染リスクも予防できます。
ベランダはもちろん、衛生面から玄関・下駄箱周りへの侵入も対策すること。窓を空ける際は、猫がふれたり舐めたりしても安全なように、定期的な清掃や消毒が望まれます。
入院の可能性も加味して、お世話を任せられる人を確保する
妊娠中は体調が悪くなることも多くあります。普段より眠くなる人・動きが鈍くなる人・起き上がれないほどの倦怠感がある人……体調不良のタイプや重さは千差万別です。
愛猫のお世話まで手が回らないことはもちろん、症状によっては緊急入院・長期入院の事態も考えられるでしょう。
万が一に備え、家族・親戚・友人・ペットシッターなど、お世話をお任せできる相手の確保が求められます。事前にお願いしておくことで、精神的な安心にもつながるでしょう。
出産後のお世話の役割分担をしておく
出産後は体力的な問題や、赤ちゃんによっては夜泣きでお母さんが夜眠れないなど、猫のお世話まで手が回らなくなることが多いもの。「イライラして猫に当たってしまった」のような悲劇を招かないためにも、パートナーとの役割分担が大切です。
出産直前直後は、心身ともに余裕がない傾向に。体調が落ち着いている時期に、あらかじめ家族と話し合っておきましょう。餌・トイレ・ブラッシングなど、日頃のケア方法を覚えてもらうだけでも安心感を得られます。
トイレのお世話はなるべく家族にお願いする
猫のお世話のなかでも、トイレ関連はなるべく家族にお願いするほうが望ましいとされます。トキソプラズマ症に感染するリスクがあるだけではなく、屈んだり立ち上がったりなどの動作が体の負担になりかねないからです。
普段はトイレのお世話を自分でやっている人も、妊娠中だけはパートナーにお願いすると良いでしょう。
ただし、猫の便は上でもお伝えしたように、できるだけ早く処理することも大切です。家族が誰もいない時に猫が便をしたら、使い捨ての手袋をして処理をしましょう。終わったら石鹸でしっかり手を洗うことも忘れずに。
猫だけで静かに過ごせるスペースを作る
妊娠中はもちろん、出産後は猫のライフスタイルも大きく変わります。赤ちゃんを感染から守るために、猫の生活空間が制限されることもあるでしょう。また新しい臭いや夜泣きなど、外的刺激によって猫がストレスを感じやすくなります。
愛猫のメンタルを少しでもケアするために、猫だけで静かに過ごせるスペースを作るのが理想的です。赤ちゃんのベッドからなるべく遠く、臭いや声が届きにくい場所に、リラックススペースを用意してあげましょう。
新しい環境に慣れるための準備を始める
猫が少しでも新しい環境に慣れるためには、妊娠中の段階から準備を始めます。たとえば赤ちゃんの声をYouTubeで聞かせたり、早期からベビーベッドを設置したりなど『出産後の暮らしのシミュレーション』を進めていきましょう。
出産後にお世話をする人が変わる場合は、当人とコミュニケーションをとる時間を増やすのもおすすめです。
猫の爪や被毛のケアはしっかりと
人獣共通感染症のなかには、猫のひっかき傷やマダニを感染源とするものも存在します。妊娠を機に、愛猫の爪や被毛のケアを見直してみましょう。
爪切りが苦手な子は、新しい爪とぎやマタタビパウダー(猫によっては与える量に注意)なども活用しつつ、清潔な状態を維持できるように努めます。トイレ掃除やベッド掃除なども徹底し、家全体の衛生状態を高めましょう。
つわり対策には『臭いケア』も肝心
妊婦さんを悩ませるつわりの対策では、猫に関連する『臭い』のケアも重要です。とはいえ、どの臭いに不快感を抱くのかは人それぞれ。たとえば猫や排泄物の臭いは平気でも、芳香剤やフードの臭いが辛いケースもあるでしょう。
臭いに苦しんだときに備え、あらかじめ『猫が入れない部屋』を確保しておくのも一つの手段です。臭いから逃げられる空間があるだけでも、ストレスを緩和できる可能性があります。
空気清浄機やペット用消臭スプレーなども導入しつつ、自分ならではの臭い対策を進めていきましょう。ただしトイレやフードボウルの場所を変える際は、猫にストレスを与えないように毎日数cmずつズラすように努めてください。
新しい環境に戸惑うのは、猫も同じ。心理的なケアを心がけて

猫からすると、人間の妊娠・出産の事情などわかりません。「飼主が構ってくれなくなった」「餌やトイレのケアが雑になった」「知らない人間(赤ちゃん)が急に増えた!」など、不満・寂しさ・戸惑いなどネガティブな感情を抱えてしまいがちです。
どれだけ入念に準備しても、ペットのストレスがゼロの状態で新生活!……というわけにはいかないのが現実です。とはいえ妊娠・出産時期では、愛猫のケアが後回しになってしまう状況も止むを得ません。
妊娠・出産では、人・猫ともにどうしてもストレスが多い環境になります。その結果、思わぬ事故やケガにつながるリスクもあります。人間側に余裕がなくなりやすい時期だからこそ、家族や友人の手を借りることも前向きに検討することが望ましいでしょう。
人間とペット、両方の安全を担保する方法を探してみよう

今回は、妊婦さんや赤ちゃんが猫と暮らす際の注意点を紹介しました。
妊娠・出産期のペットのお世話は、1人では限界を感じやすいものです。人間とペット、両方の安全や快適を担保するためにも、周囲のサポートをお願いしながら新しいライフスタイルを模索していきましょう。













