- 動物園獣医師は狭き門で少数しかいない
- 病気と多くの動物そのものの両方について知識が必要
- 健康診断や採血には臨機応変さと技術が必要不可欠

獣医師と聞いて真っ先に思い浮かべるのは動物病院の獣医師ではないでしょうか。ペットと暮らす人には身近な存在でもありますね。
獣医師の仕事は幅広く、牛や豚、鶏など産業動物に関わる獣医師もいれば、公務員や会社員として働く獣医師などもいます。そして少数ではあるものの、動物園で働く獣医師もいます。
今回は動物園で働く筆者が、動物病院の獣医師とは少し異なる動物園獣医ならではの仕事の一部を紹介します。
◆執筆・監修:獣医師プロフィール
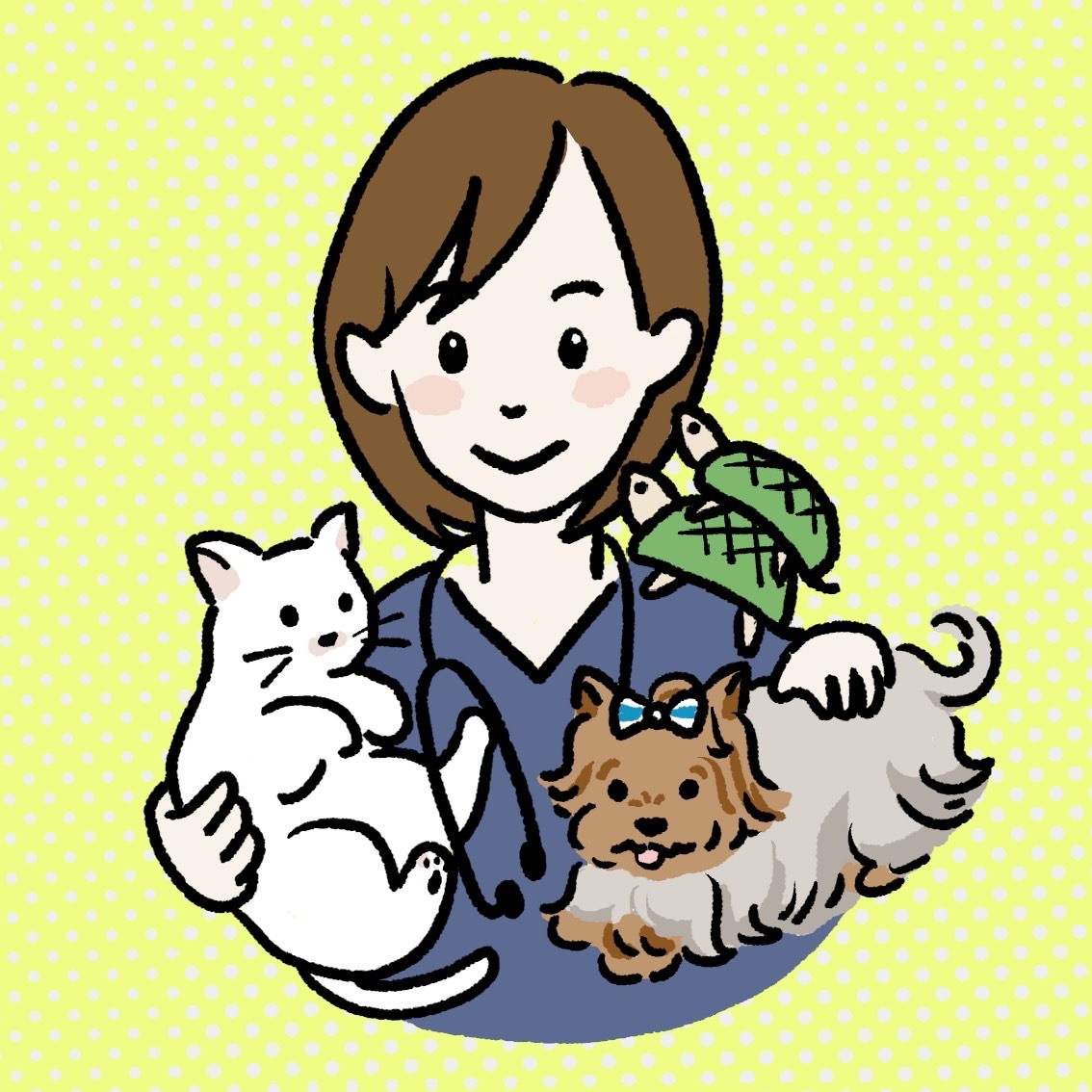
岩手大学で動物の病態診断学を学び、獣医師として7年の実績があり、動物園獣医師として活躍中。動物の病態に精通し、対応可能動物は多岐にわたる。
日本でたった300人!“狭き門”な動物園の獣医師

獣医師自体、それほど人数が多いわけではありませんが、その中でも動物園獣医師は大変少数です。
【分野別】全国に4万人の獣医師
令和4年3月の報告で、
獣医師免許を保有している人は約4万人です。このうち、約4割が動物病院の獣医師で、1割が牛など産業動物の獣医師です。
その他の大多数が公務員で、製薬会社などの企業に勤める人もいます。
動物園獣医師の数は?
日本動物園水族館協会に掲載されている名簿を確認してみると、獣医師免許保有者は300人弱です。
この中には園長などすでに臨床現場から離れていたり、獣医師免許を持っていても飼育職や教育普及などの仕事をしている人も多いため、動物園で日常的に診療業務などに従事している獣医師はさらに少ないと言えます。
動物園獣医師のお仕事とは?現役獣医師が解説

動物病院での獣医師の役割は、動物の診療と治療です。一方で、動物園獣医師の仕事は動物の診療と治療のみではありません。
ここではあまり知られることのない動物園獣医師の仕事の一部を紹介します。
動物園獣医師の仕事内容
動物園獣医師の役割は、動物園によっても異なりますが、多岐に渡るのが一般的です。飼育職員と同様に飼育業務を行うこともあれば、教育活動を担当することもあります。
動物に接する仕事だけでなく次のような業務を担うなかで動物園全体の運営に関わるのが動物園獣医師の特徴です。
- 動物の診療業務
- 動物の飼育業務
- 死亡した動物の解剖
- 園内の防疫関連業務
- 教育普及活動
- 広報関連業務
- 園内イベントへの従事
- 他園との動物交換などに関する事務業務
- 標本の作製
動物園での1日のスケジュール
動物園での1日は朝一番の動物達の健康状態を把握することから始まります。それから入院動物の治療をしたり、予定していた手術や検査を行うなどの業務を開始しますが、計画通りに1日を終えられることはそう多くありません。
急患の報告があればそちらを優先させますし、動物園の動物に何もなくても、例えば近隣で高病原性鳥インフルエンザが発生したなどの事態になれば防疫業務でてんやわんやになる日もあるのです。
病院獣医師とは違う!動物園獣医師に必要な姿勢
動物の病気とその動物の生態には大きな関連があります。例えば紫外線が必要な動物を太陽の当たらない屋内で飼育すれば病気になります。
動物病院で診る動物の多くは生態がわかっていて健康を保つための飼育環境に迷うことは多くないでしょう。
一方で、動物園動物のほとんどは生態が不明で飼育環境も試行錯誤です。動物園獣医師にとっては病気について学ぶことと同じくらい、動物そのものについて学び続ける姿勢が必要です。
動物たちの健康はどう守られる?動物園の健康診断を紹介

「動物園でも健康診断をするの?」と聞かれることがあります。実施したいのはやまやまですが、難しい現状もあります。
健康診断は可能な範囲で実施
健康診断のためには、動物にさわったり体重計に乗せたり聴診器などの器具を体につける必要があります。ペットではそれほど難しいことではありませんが、動物園動物の多くは一定以上の距離に近づくことすらできません。ペットでは当たり前の健康診断も難しいのです。
しかし、諦めているわけではありません。動物によってはトレーニングを取り入れて健康診断を行うこともあります。
動物や個体の特性を見極め可能な範囲で健康診断を行うこともあります。例えばレッサーパンダはリンゴが大好物です。
食べている間は何をされても気にしないことが多いため、飼育職員にリンゴを与えてもらっている間に獣医師が採血をしたり、エコー検査をすることがあります。
一番重要な仕事は「日常の観察」
上でお伝えしたように、動物園では体重や採血結果などの数値を元にした健康管理は難しいことも多いです。そのため、日頃から動物を観察する目を養うことが重要です。
歩く・食べる・寝る・遊ぶといった行動の変化や、糞や尿などの排泄物の確認など、職員は五感をフル活用して動物の健康に気を配っています。
特に飼育職員の観察眼は大変鋭く、獣医師としてはいつも「よくこんな小さな異変に気づいてくれたなぁ。」と尊敬の念を抱きます。
動物園動物の採血について

病気の診断において血液検査は最重要項目のひとつです。ここでは動物園での採血について紹介します。
どうやって採血するの?
採血のためには不動化、つまり動物が動かないようにする必要があります。不動化の方法には人が動物を押さえる方法(保定)と麻酔をかける方法があります。
ペットでは保定が一般的ですが、動物園動物の多くは保定することができず麻酔を利用することも多いです。
麻酔をかける方法はさまざまです。動物を網や狭い場所に追い込み逃げられない状態にして注射や吹き矢、麻酔銃を利用して麻酔薬を入れることもあります。
小型の動物であればケージごと袋などで覆い、簡易的な密閉空間を作って麻酔のガスを送り込むこともあります。
動物が抵抗する際に怪我をしないかどうか、関わる職員の安全は守られるかなどの綿密な計画が必要ですし、病気などで弱っている動物に負担をかけてまで採血する必要があるのかどうかという点から議論が必要なケースも多いです。
どこの血管から採血するの?
麻酔などで採血できる状態になったとして、次の問題は採血部位です。犬や猫の場合、首・前足・後ろ足などの血管から採血するのが一般的です。動物園動物の場合はどこの血管を利用することが多いのか、動物種ごとに紹介します。
動物種によって試行錯誤の哺乳類
哺乳類では犬や猫と同様に、首・前足・後ろ足などの血管を利用できます。また、尻尾の血管から採血することもあります。
ただし、小型でずんぐりとして尻尾も短い動物、例えばモルモットやプレーリードッグなどの動物は採血が大変難しいです。
首も足も短いうえ脂肪が多く、なかなか血管が見つかりません。個体によって利用できそうな血管が異なるため、麻酔が効いたら大急ぎであちこちの血管を探ります。
同じ哺乳類でも、アシカやアザラシなどの海獣類は首の血管を利用できません。ヒレの間の血管を利用したり、背骨に沿った血管を利用する方法もあります。
これらの動物は水中で過ごす時間が多く血管が収縮していることも多いため、採血の前にまずヒレなどを温かいお湯などで温めて血管を怒張させるひと手間が必要です。
採血部位は多岐にわたり採血が難しいことも多い鳥類や爬虫類

鳥類の採血は難易度が高いことも多いです。採血部位は鳥の種類によっても異なりますが、首・翼の裏側・足の血管を利用することが多いです。
種類によっては捕まえただけでショック状態になり、命に危険が及ぶ場合もあります。骨も繊細なので、押さえた時に翼や足などを痛める危険もあります。
ヘビ・カメ・トカゲなどの爬虫類も採血が難しい動物のひとつです。尻尾の血管を利用できる場合もありますが、カメは尻尾が短い種も多く、首の血管から採血することがあります。カメでは甲羅の内側に沿った血管を利用することもあります。
採血できるようになるためには
採血ひとつとっても、動物によって、またその個体によって臨機応変さが求められるのが動物園獣医師です。対応するためには日頃から情報収集を積極的に行うことも重要で、学会発表や論文、獣医師同士の勉強会などでの学びが欠かせません。
私は最近、齧歯類で前歯の根本から採血ができるということを知ったのですが、残念ながら上手に血液を採れたことがありません。
情報と共に技術の向上も大切なのです。
獣医師は動物園の裏方として動物の健康を守る役割

今回の記事では、動物園獣医師の仕事について紹介しました。動物病院の獣医師とはまた異なる難しさや悩みがある分野ですが、私自身は飼育職員との協力で動物の病気を未然に防ぐことも可能な点などに大きな魅力を感じています。
普段は表に出る機会の少ない動物園獣医師ですが「診療室ツアー」などのイベントのある動物園もあります。興味があればこのような企画にも参加してみると、より一層動物園を楽しめるかもしれません。
以下の記事では、34歳になった五月山動物園のウォンバットを紹介しています。ぜひチェックしてみてください!




