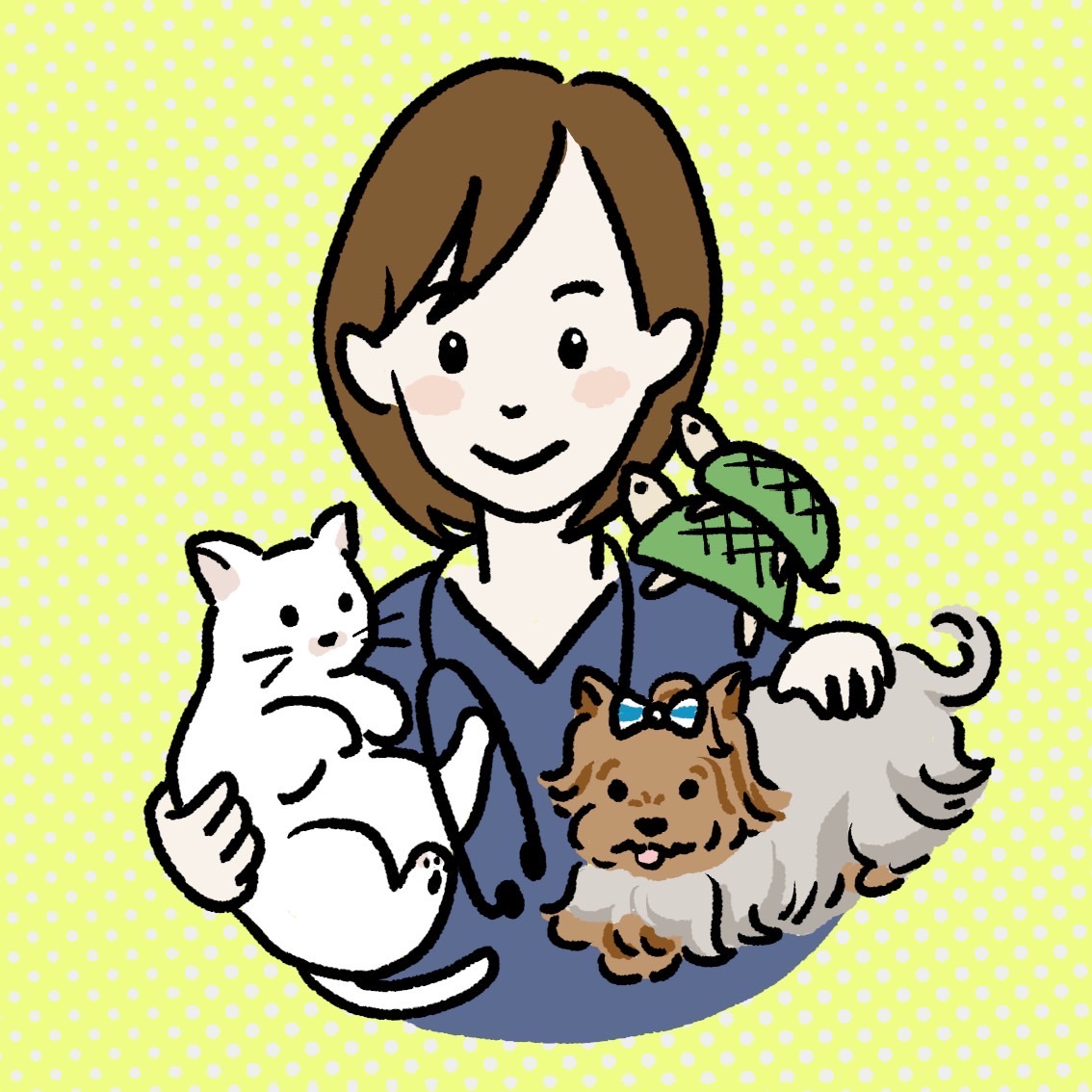- 動物園水族館の多くが『日本動物園水族館協会』に加盟し互いに協力している
- 希少種のなかでも『種別調整対象種』の繁殖には『種別調整者』が大きく関わる
- 動物園水族館は、日常的に動物を貸し借りする
- 日本の動物園水族館において動物の維持のためにはJAZAが欠かせない

どんな動物でも、赤ちゃんのかわいさは格別ですね。動物園水族館の職員にとっても、繁殖に関わる仕事は大変やり甲斐のある仕事です。
しかし、動物園や水族館での動物の繁殖事情はほとんど知られていません。今回の記事では、動物園で獣医師として働く筆者が、動物園水族館の繁殖事情について詳しくお伝えします。
動物園・水族館の役割は4つ。動物園での繁殖の意義とは

繁殖についてお伝えする前に、まず、動物園や水族館そのものの存在について解説します。みなさんにとって動物園や水族館は、動物に会うためのレジャー施設でしょう。しかし動物園や水族館の役割はそれだけではありません。
公益財団法人日本動物園水族館協会(JAZA)について
動物園や水族館の解説をする際、必ずお伝えしなくてはならないのが、『公益財団法人日本動物園水族館協会』の存在です。動物園や水族館の関係者には、JAZA(ジャザ)と呼ばれています。JAZA(Japanese Association of Zoos and Aquariums)とは、日本動物園水族館協会の略称です。
2025年4月1日の時点で、日本の動物園水族館のうち、動物園91園館、水族館49施設がJAZAに加盟(※1)しています。
時々「動物園同士はライバル関係なの?」と聞かれることがありますが、まったく反対です。JAZAに加盟しているすべての動物園水族館は、生き物や環境を守るために協力しあっています。
また、国際的には、世界動物園水族館協会(WAZA=ワザ)が存在します。WAZAには世界各地の動物園水族館が加盟し、さらに国際的な視野、地球規模での生き物及び環境の保護を行っています。
動物園水族館の4つの役割
JAZAは、日本の生き物や、生き物が生息する環境を守るため、動物園水族館の役割として下記の4つ(※2)を掲げています。
① 種(しゅ)の保存
地球上の生き物を絶やさないように維持する役割
② 教育・環境教育
動物や、動物が住む環境そのものを守るための教育活動
③ 調査・研究
生き物の生態を詳しく調べ、動物たちが動物園や水族館で快適に暮らせたり繁殖できたりすることにつなげる活動
④ レクリエーション
人々が楽しい時間を過ごしながら、生き物について考えることができる場を提供する
動物園や水族館での繁殖は、直接的に『種の保存』に貢献するだけでなく、繁殖を通して教育活動を行ったり、研究をおこなったりすること、また、産まれた赤ちゃんをお客様に見ていただいて楽しんでいただくことにつながるのです。
動物園水族館における希少種『種別調整対象種』の繁殖について

動物園・水族館での繁殖は、動物達の自由に任せているわけではありません。各園館で繁殖計画を立て、管理しています。特に、希少種のなかには『種別調整対象種』と呼ばれ、全国の動物園・水族館が協力しあって繁殖に力を入れている種もいます。
CITES(サイテス)って知ってる?動物園・水族館における希少種とは
動物園や水族館には、希少種とそうでない種がいます。希少種というのは、CITES(※3)サイテス=絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約の附属書に掲載されている種のことです。
動物園水族館で飼育する野生動物の多くがCITESに掲載されている希少種です。
自分の興味のある動物が、希少種かどうか知りたい場合は、その動物園のホームページの動物紹介のページや、動物園の柵などにかけてある種名板(その動物の名前などが書かれているボード)などを見てみると良いでしょう。
JAZAは、希少種のなかでも、特に守る必要がある種を『種別調整対象種』として、全国の動物園・水族館での繁殖を推進しています。
種別調整対象種はこちらで確認してください【種別調整対象種|日本動物園水族館協会】
※3:ワシントン条約(CITES) (METI/経済産業省)

種別調整対象種の繁殖を管理する種別調整者について
種別調整対象種には、ひとりの種別調整者が選出されます。
種別調整者は、担当種に関して、JAZA加盟園館すべてから各個体の血統データを集め、コンピューター上で管理します。なぜなら、いくらたくさん繁殖させたいからといって、単純に個体数を増やせばいいというわけではないからです。
親子やきょうだいなど、近すぎる血縁関係での繁殖を繰り返すと、遺伝的な先天疾患などのリスクが伴ったり、遺伝子の多様性が失われたりするなど、種の保存にとってマイナスの要素が増加します。
そこで、種別調整者が、日本国内すべての個体のデータを使い、繁殖に際して血統的に最適な雄と雌を算出して繁殖を進めるのです。
難しい仕事ですが、種別調整者は特別な教育を受けた人がなるわけではありません。JAZAに加盟している動物園水族館の飼育係や獣医師が、ソフトウェアの使い方などを学びながら担当します。
少し話が逸れますが、動物園水族館の飼育係や獣医師は、その園館で動物のお世話をするだけでなく、動物に関するデータベースの構築や、解析の業務も行っています。
希少種(種別調整対象種)の繁殖の具体的な流れ
みなさんがよく動物園や水族館で見かけるフンボルトペンギンは、種別調整対象種の一種です。
フンボルトペンギンを飼育するTierzine動物園という動物園で、この種を繁殖させることになったとしましょう。
まず、種別調整者が、Tierzine動物園にいる雌雄の個体に対し、それぞれの異性個体の血統的なランキングをつけます。
Tierzine動物園にいる雄①に対して、
ランキング1位はA動物園の雌①
ランキング2位はB水族館の雌②
ランキング3位はC動物園の雌③
というようなイメージです。
ランキングを元に、園館同士で協議して、ペアの相手を決めるというのが大まかな流れです。
ブリーディングローン(BL)という仕組み。動物園・水族館では動物の貸し借りが一般的

種別調整対象種では、繁殖を計画する園館のなかに、繁殖に最適なペアがそろっていないことがほとんどです。そこで、JAZA加盟の動物園・水族館のあいだでは、動物の貸し借りがごく一般的に行われます。
ブリーディングローン(BL)の解説
フンボルトペンギンの例を使って引き続き解説します。
Tierzine動物園において、飼育している雄個体①と、繁殖相手としてのランキングが2位である、B水族館の雌個体②のペアで繁殖させることに決まったとします。
この場合、Tierzine動物園は、B水族館から雌個体②を借りることになります。
繁殖のための動物の貸し借りの仕組みをブリーディングローンと言い、動物園・水族館ではBL(ビーエル)と呼んでいます。BLは、種別調整対象種だけに適応されるわけでなく、どのような動物でも使うことのできるシステムです。
貸し借りと言うと、しょっちゅう動物が移動するように聞こえるかもしれませんが、実際には特別な理由がない限り、一度BLで移動した動物は、一生を移動先の園館で過ごします。
希少種以外の動物も移動することがある
希少種以外の動物や、希少種であっても種別調整対象種以外の動物の場合、繁殖に関してJAZAが管理することはありません。しかし、それぞれの園館での血統管理が行われていて「そろそろ新しい血を入れた方がいい」と判断することもあります。
また、繁殖に関わる場面でなくても、動物が欲しいこともあります。
反対に、動物園・水族館では、飼育スペースなどの問題で、動物を他の園館に出したいという状況も出てくることがあります。
日本の動物園・水族館が動物を新しく入れたいとき、反対に、動物をどこかに出したいとき、どちらの場合も、JAZAを介して園館同士で個体の移動を行います。
BLを使うだけでなく、相手の園に無条件で動物を譲渡する方法や、お互いに必要な動物を交換する方法などがあります。
いずれにしても、動物園・水族館が動物を管理するためには、JAZAという全国的なネットワークが欠かせません。
動物の赤ちゃん誕生はさまざまな計画に基づいている

今回紹介した、動物園や水族館での繁殖に関する取り組みは、みなさんが知らないことばかりだったのではないでしょうか。記事を読んだ皆さんが「へぇ、そうだったんだ!」と驚き、動物園や水族館での赤ちゃんの誕生の裏にある、さまざまな計画や職員の努力に少しでも興味が湧いたなら、とてもうれしいです。