- けいれん・よだれ・意識を失うなどの発作があったら安静にしてすぐ病院へ
- 発作を起こしやすい犬種がある
- 遺伝や脳腫瘍などを原因としたてんかんも
- 飼主は冷静に対処できるように知識を身につけよう

◆執筆・監修:獣医師プロフィール
監修者
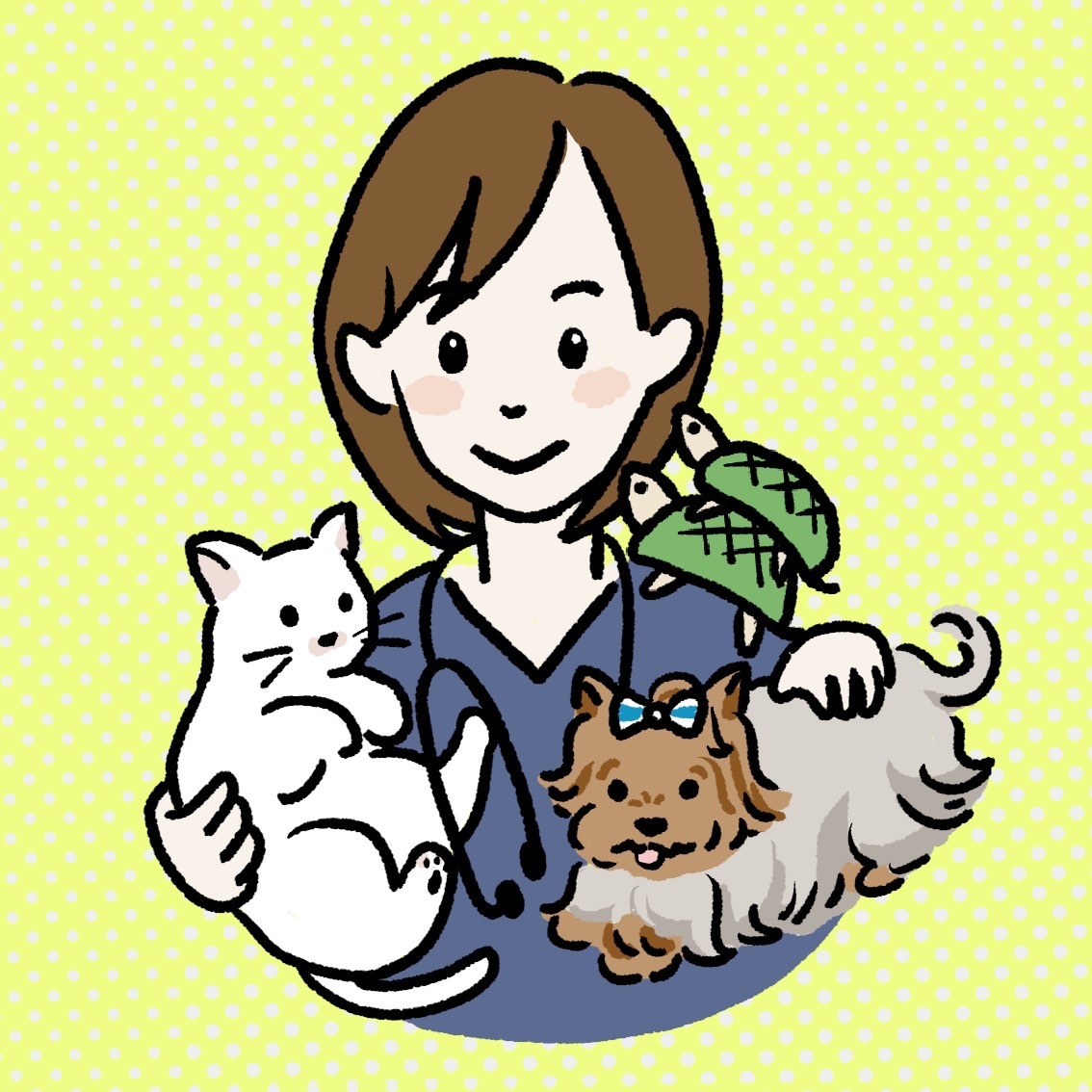
ttm 医師
岩手大学で動物の病態診断学を学び、獣医師として7年の実績があり、動物園獣医師として活躍中。動物の病態に精通し、対応可能動物は多岐にわたる。
愛犬が突然けいれん発作を起こしたら慌てる飼主も多いでしょう。そのけいれん発作は『てんかん』かもしれません。実は犬のてんかんはそれほど珍しい病気ではないということを知っていますか?
もし発作が起きた場合に備えて、飼主が正しい知識を持ち、冷静に行動することが愛犬の命を守るカギになります。本記事では、てんかんをもつチワワと共に暮らした経験のある筆者が、発作の見極め方や対処法をわかりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。
唐突に起こる発作、犬のてんかんとは?

てんかんとは、脳にある神経細胞(ニューロン)の異常な電気活動により、発作があらわれる脳疾患のことです。突発的に運動機能や感覚、自律神経系などに障害が出ます。人間だけでなく犬にも現れる症状です。
見分けにくい!てんかん発作の特徴
てんかんの典型的な症状として、けいれん・よだれ・意識を失う・尿失禁などが現れます。てんかん以外にも似たような症状を引き起こす病気が多いため、見極めが困難です。たとえば、食中毒・低血糖・心不全・熱中症など、さまざまな病気が考えられます。
また、初期症状は『震え』から始まることも多く、寒さや怖さでも震えるため、てんかんかどうかの判断が難しいといえます。
判断材料のひとつとして重要なのが、発作の持続時間です。通常のてんかんであれば、2〜3分程度で治ることが多いと言えます。はじめての発作をおこした時に、数分で何事もなかったかのようにケロリとしている場合は、てんかんである可能性も低くありません。
ただし、発作が長時間続くてんかんもあります。5分以上続いたり、短い発作が連続して長時間回復しない状態を『重積(じゅうせき)』と呼び、脳へのダメージが大きくなる傾向があります。最悪の場合は、命に関わる可能性も。
通常のてんかんも、なんども繰り返すうちに『重積』に移行することがあります。
はじめての発作が現れたら愛犬から目を離さず、すぐに病院に連れていくことが非常に重要です。
てんかんを引き起こしやすい犬種は?

てんかんには、若年期に多く原因が特定できない『突発性てんかん』と脳に明らかな原因がある『構造性てんかん(旧:症候性てんかん)』があります。
突発性てんかんは、明らかな異常や原因が特定できず、遺伝的な要因により引き起こされるとも考えられています。比較的若い、生後6ヶ月〜6歳までに最初の発症が起きることが多い傾向があります。
どのような犬種でもおこりますが、チワワ・トイプードル・マルチーズなどの一部の小型犬で比較的多くの報告があります。また、ビーグル・ボーダーコリー・ジャーマンシェパード・シベリアンハスキーなどでは遺伝との関連が論文で示唆されています。
また、構造性てんかんは脳の構造的な異常(脳腫瘍や脳血管障害など)が原因で引き起こされます。発作のほかに、徘徊や歩行異常がみられることがあります。発作の原因はさまざまで、体の異常を知らせるサインとして現れる場合が多いでしょう。
てんかん発作が起きたとき、愛犬のためにできること

てんかん発作は突然現れます。実際に発作が起こった場合、落ち着いて対応できるように気をつけたいことを紹介しますので、とっさに対応できるようにしておきましょう。
突然のてんかん発作!重要なのは『記録』
発作が起こったとき、最初にすべきことは、体や頭をぶつけないように安全な場所に移してあげることです。移動できたら、発作の時間を測りましょう。3分以上続く場合は、病院に搬送することも視野に入れて行動してください。5分以上続くと後遺症が残ることも。
突然の発作に直面すると、飼主はどうしてもパニックに陥りがちです。しかし、そんなときこそ飼主の冷静な判断と行動が、愛犬の命を守ることにつながります。
発作中の行動や時間・前後の様子をしっかり観察し、必要に応じて動画を撮影するなど、落ち着いて対応することが求められます。
発作が起こったときに絶対にしてはいけないことは、大声で呼びかけたり、揺すって無理に起こそうとするなどの刺激を与えること。脳出血なども考えられるため、安静にしましょう。
また、口に手を入れるのは危険なので絶対にやめてください。発作により体が硬直し、力がコントロールできないので、強く噛まれてしまいます。愛犬を守ることも大切ですが、飼主が怪我をしないように立ち回ることも重要です。
てんかんとは『うまく付き合う』日常のケア
突発性てんかんには完治がなく、一生付き合っていくものです。抗てんかん薬で発作の頻度や強度を抑えながら生活する必要があります。日常生活ではストレスが溜まりすぎないように注意し、発作が起きたときの記録を続けましょう。
構造性てんかんの場合は原因疾患の治療で症状が改善する場合も。脳腫瘍であれば手術・放射線治療、脳炎であれば抗生物質などが考えられます。
一人で抱え込まず、かかりつけの獣医師と連携して治療や経過観察を行うことが大切です。
慌てず、冷静に対応する力を。飼主の心構え
日頃から発作の備えとして、夜間や休日でも診察してくれる動物病院を調べておくことも、いざというときの安心につながります。
診断には血液検査やレントゲン・MRI・CTスキャンなどの検査が必要で、これらを組合せて慎重に進められます。とくに、てんかんの診断はほかの病気の可能性を排除しながら慎重に行われます。確定までにある程度の時間がかかることもあります。
突然発作が起きた際、愛犬を安全な場所に抱きかかえて運ぶ必要があることも想定し、緊急時の移動手段や抱っこの方法などを事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。飼主自身の体力的な負担も考え、家族やパートナーと協力体制を整えておくことも有効です。
てんかんの診断を受けたら。病気との向き合い方

愛犬がてんかんと診断されたとき、多くの飼主はショックを受けます。不安や戸惑いが押し寄せるのは当然のことです。しかし、てんかんは適切な治療とケアによって、犬も飼主も穏やかな日常を取り戻せる病気です。
大切なのは、てんかんを特別視し過ぎず、ほかの慢性疾患と同じように『てんかんと共に生きていく』意識を持つこと。発作の頻度や重さには個体差があり、薬の調整や生活リズムの工夫によって、発作のコントロールが可能になる場合もあります。
また、SNSやオンラインコミュニティで、同じ悩みを抱える飼主たちとつながることも心の支えになります。「うちの子も頑張ってる」「こんなふうにケアしている」といった実体験の共有が、不安を和らげてくれることもあるでしょう。
てんかんに対する最低限の知識をつけておこう

震えやけいれんといった発作は、てんかんだけでなくほかの重大な疾患が原因で起こる場合もあります。
自己判断で様子を見るのではなく、早期に動物病院で診察を受けることが何より大切です。発作の持続時間や前後の様子を記録し『迷ったら病院へ』と即座に行動することで、愛犬の命を救える可能性が高まります。
正しい知識と冷静な対応、そして獣医師との連携がてんかんであってもそうでなくても、愛犬と安心して暮らす日々を守るポイントです。不安なときは一人で抱え込まず、周囲の支援や情報を活用して、愛犬と一緒に前を向いて歩んでいきましょう。













