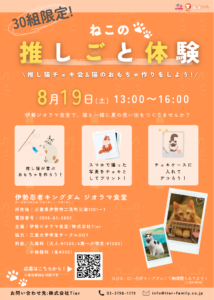- 秋は気温や湿度の変化が大きく、体調を崩しやすい
- 適正体重の維持やストレスケアなど、日常的な習慣で防げる病気も多い
- 過ごしやすい季節こそ、小さな変化も敏感に察知しよう

暑い夏が終わり、過ごしやすい秋がやってきました。秋は食事に運動にと、健康に関する習慣に積極的に取り組みやすい時期ですよね。
しかし猫を飼育している人にとって、秋は注意すべきポイントが多い季節。今回は『秋にかかりやすい猫の病気・疾患』を紹介します。愛猫の小さな変化を見逃さず、心身の健康をサポートしていきましょう。
水分摂取量の減る時期だから気をつけたい【泌尿器系の病気】

夏は暑くてゴクゴク水を飲んでくれていた猫も、涼しい季節になると飲水量が下がる傾向に。ここでは、飲水量の減少に由来する『泌尿器系の病気』を紹介します。
膀胱炎|膀胱に炎症が起こる病気
膀胱炎は、さまざまな原因によって膀胱に炎症が生じる病気です。飲水量の減少やストレス、細菌感染などによって発症します。頻尿・血尿・排尿時の痛みなどの症状が現れ、放置すると炎症産物などが尿道に詰まって『尿道閉塞』という命にかかわる状態になってしまいます。
膀胱炎は、一度快方に向かっても再発しやすいのが特徴。初期症状としては『1回の排尿量が少ない』『トイレに行く回数が増えた』などがあげられます。十分な量の水を飲み、清潔なトイレ環境を用意することが予防につながります。

尿路結石症|尿路(腎臓から尿道まで)に結晶・結石ができる病気
尿路結石症は、腎臓・尿管・膀胱などの尿路に結石・結晶ができる病気です。初期症状としては頻尿や尿にキラキラした結晶が混ざるという症状があげられ、症状が進むと血尿・トイレ以外での排尿・排尿時の痛みなどが現れます。結石が尿管や尿道に詰まると、尿路閉塞という状態になり、急性腎不全や尿毒症をひきおこし、命にかかわります。
予防方法は、飲水量の維持・ストレスケア・栄養バランスの整った食事などが代表的です。とくにオスはメスと比べて尿道が長く、結石が詰まりやすい傾向にあります。
以下の記事では、なかなか水を飲んでくれない猫への対処法をまとめています。今回の記事とあわせて、ぜひ参考にしてください。

換毛期だから気になる【被毛・皮膚に関連する病気】

猫にとって秋といえば、1年に2回の換毛期シーズン。夏気から冬毛に生えかわる時期にも、さまざまな病気を患いやすくなります。大量の被毛が抜け、皮膚が繊細なる秋に注意したい病気をチェックしていきましょう。
毛球症|お腹の中に毛球ができる病気
毛球症は、猫が飲み込んだ毛が胃腸に蓄積され、毛球になることでさまざまな症状を引き起こす病気です。とくにペルシャやメインクーンなど、豊かな毛量を持つ描種は要注意。症状としては、食欲低下や頻繁な嘔吐などが現れます。
何度も吐こうとして食道が炎症を起こしてしまうことも。重症になると、毛球が詰まっている部分の血行が悪化し、腸管に穴が空いてしまうケースもあります。予防方法としては、定期的なブラッシングでの被毛ケアや、食事・サプリメントでの腸内ケアが効果的です。
真菌症|脱毛・フケ・炎症などが現れる『カビ』の病気
真菌症は、代表的な人獣共通感染症の一つ。真菌とは『カビ』のことで、『カビ』が皮膚に侵入し、さまざまな症状を引き起こします。換毛期には皮膚のバリア機能が低下しやすくなるため、普段以上に感染リスクが上がる傾向にあります。
とくに脱毛・フケの症状が特徴的な『皮膚糸状症』や、痒みや炎症が現れる『カンジダ症』などが有名。真菌は高温多湿の環境で増殖しやすいため、室内を換気しつつ清潔な状態を保つことが予防につながります。
食欲の秋は猫にも訪れる!?【肥満に関連する病気】

夏バテ気味で食欲が少なかった子も、涼しい秋になると食欲が旺盛になることがありますよね。秋は、冬に備えて脂肪を蓄えやすい時期。つまり肥満のリスクが高まる季節です。ここでは、猫の肥満と関連性が深い病気を紹介します。
関節炎|関節の炎症で痛みを感じる病気
関節炎は、関節の軟骨が損傷したりすり減ったりすることで、炎症や痛みを引き起こす病気の総称です。猫の関節炎では『変形性関節症(関節の軟骨や周辺組織が変形し、炎症を起こす病気)』が一般的で、肥満や加齢などによって発症リスクが上がります。
初期症状では、グルーミング回数や運動量の減少が現れます。重症化すると、痛みで歩行すら困難になってしまうことも。適度な運動や食事ケアによる体重管理や、滑り防止のための床材の見直しなどが予防につながります。
糖尿病|肥満で発症リスクが上がり、命にもかかわる病気
糖尿病は、肥満・運動不足・ストレスなどによって引き起こされる病気です。体内のインスリンの分泌量が不足したり、インスリンの働きが弱まることで、血糖値の高い状態が続きます。
初期症状としては、飲水や排尿回数の増加・食欲が上がるのに体重が減少するなどがあげられます。
症状が進むと嘔吐や脱水などが現れ、最終的には死に至ることもある病気です。予防策としては、食事管理の徹底があげられます。とくに繊維質の多いフードは、食後の血糖値の上昇を抑えやすく、満腹感も得やすいでしょう。
肝リピドーシス(脂肪)|体重管理が予防に直結する病気
なんらかの原因で絶食状態が続き、エネルギー不足になると、体は体脂肪をエネルギーに変えて利用しようとします。その際、動員された脂肪の代謝が追いつかず、肝臓に蓄積して急激に肝機能が低下する病気が肝リピドーシスです。
猫は肝臓での脂肪代謝の能力が低いため、この病気になりやすいですが、特に肥満気味の猫は高リスク。初期症状では食欲不振や嘔吐・便秘・軟便などが現れ、放置すると命に関わるため、迅速な治療が必要です。
もともと肝臓に溜まっている脂肪が多い肥満猫の発症リスクが高い病気なので、適切な体重の管理が予防に直結します。
秋にも活動が活発に【マダニに関連する病気】

春と秋は、マダニの活動ピーク期。飼主の洋服や洗濯物などからマダニが侵入すると、完全室内飼育の猫でもダニ媒介感染症を患ってしまう場合があります。マダニに関連する病気を学び、対策につなげていきましょう。
猫ヘモバルトネラ症(ヘモプラズマ感染症)|息切れや貧血が現れる病気
猫ヘモバルトネラ症の感染経路は今のところ明確ではありませんが、ノミやマダニをはじめとする節足動物の媒介によって感染することがあると言われています。
赤血球の数が減少し、息切れや貧血・体力低下などの症状が現れます。進行すると、低体温・呼吸困難・ショック状態に陥る場合もあります。
幸いなことに、抗生物質で細菌を退治すれば通常は回復するケースが多い傾向に。室内飼育の徹底や、屋外の猫との接触の遮断など、外界との関わりを減らすことで感染機会を減らせます。
重症熱性血小板減少症候群(SFTS)|致死率60%の恐ろしい病気
重症熱性血小板減少症候群は、マダニが媒介するウイルス性の感染症です。初期では発熱や食欲不振などが見られ、重症化すると黄疸や出血などが現れます。人獣共通感染症であり、人間の致死率は10~30%、猫はおよそ60%の恐ろしい病気です。
重症熱性血小板減少症候群にはワクチンや特効薬が存在しません。最大の予防策は、マダニに嚙まれないことです。明確な治療法がないからこそ、早期発見と対症療法が重要になります。
気温の変化による体調不良にも注意!

夏から秋は、気温や湿度も大きく変化する時期。外的環境が変わると、知らず知らずのうちに心身にも負担がかかっていることもあります。
『季節の変わり目は体調を崩しやすい』は、猫にも人間にも当てはまることです。とくに食欲不振・下痢・嘔吐などは見逃さず、前後の猫の状態を観察しつつ、気になる症状がある場合は獣医師に相談しましょう。
飲水量の確保・適切な体重の維持・栄養バランスの取れた食事など、普段からの生活習慣でリスクを下げられる病気も多いものです。今一度健康の基本に立ち返り、愛猫の心身を内側からサポートしていきましょう。
過ごしやすい季節だからこそ、健康管理が大切!

今回は、猫が秋に患いやすい病気を紹介しました。
病気の進行は、見た目だけではわからないケースも多く存在しています。「元気があるから」「ごはんをよく食べるから」と安心するのではなく、愛猫の些細なサインに気づけるように、普段以上にスキンシップの機会を増やしていきましょう。