- 妊娠中は衛生面に要注意。とくにトイレのお世話は控えよう
- 散歩やコミュニケーションなどは、家族やシッターのサポートも借りよう
- 妊娠中に『赤ちゃんがいる生活のシミュレーション』を始めて、愛犬のストレスを軽減しよう

妊娠や出産は、家族のライフスタイルに大きな影響を与えます。犬と暮らしている妊婦さんは、愛犬との関わり方にも注意が必要です。
今回は、妊婦さんや赤ちゃんが犬と暮らす際に気をつけるべきポイントを紹介します。妊娠中や出産前後ならではの注意点を学び、愛犬との適切な関係性を築いていきましょう。
監修者
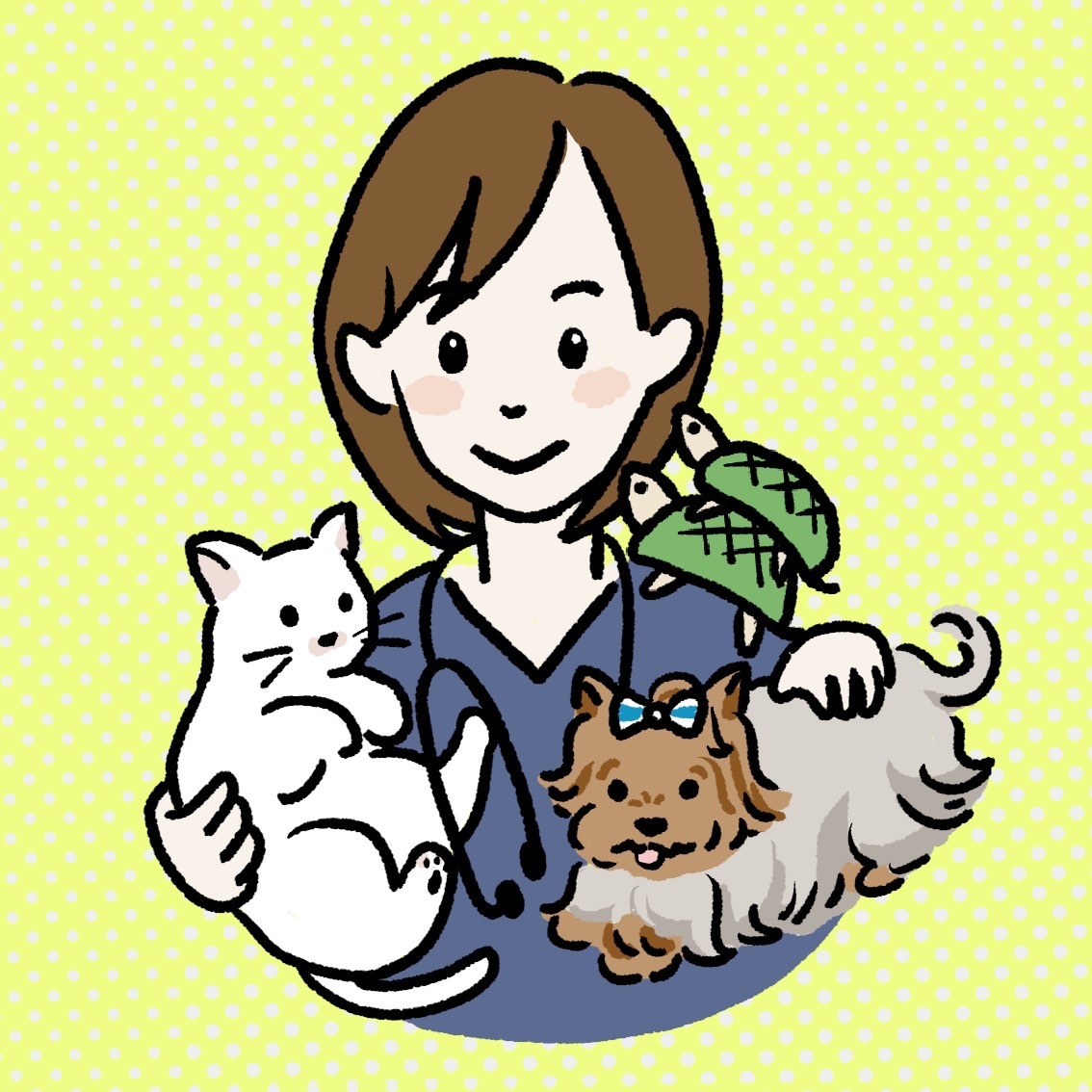
ttm 医師
岩手大学で動物の病態診断学を学び、獣医師として7年の実績があり、動物園獣医師として活躍中。動物の病態に精通し、対応可能動物は多岐にわたる。
妊婦が犬と一緒に暮らす時に注意するべき3つのこと

ここでは、妊婦さんが犬と一緒に暮らす際に気をつけたいポイントを3つ紹介します。人もペットも健やかに暮らすために必要なのは、衛生・体調・心のケア。時には家族のサポートも借りながら、ストレスを最小限にできる生活を目指しましょう。
衛生面のケアで体を守る
妊婦さんが犬と暮らす際は、衛生面のケアを徹底するように心がけます。妊娠中は免疫力が下がり、感染症を患う可能性が高まります。なるべくトイレ掃除は避け、犬に顔や手を舐めさせるのも控えましょう。
とくに排泄物のケアは、サルモネラ症を含むさまざまな病気の感染リスクを高めます。基本的には家族に任せつつ、どうしても掃除をする場合は使い捨ての手袋やマスクを利用しましょう。もちろん、掃除後はしっかり手を洗うことも必須です。
ペットの臭い対策で快適な生活を
妊娠中は臭いに敏感になる人が多い傾向にあります。何の臭いが苦手になるのかは千差万別。排泄物の臭いだけではなく、フードの臭いや愛犬の体臭、芳香剤の匂いなど、今まで気にしなかったような臭いに強い不快感を抱く場合があります。
空気清浄機やペット用消臭剤、定期的な換気などを取り入れ、ストレスの少ない環境を目指しましょう。愛犬が入ってこられない『自分が逃げ込める部屋』を作っておくと、臭いのストレスが高まったときにいくらか体が楽になります。
家族のサポートを借りよう
妊娠中の愛犬との暮らしでは、積極的に家族にサポートをお願いしましょう。散歩や餌やりなど、犬のお世話は何かと体力勝負。屈んだり立ち上がったりなど、お世話の姿勢がつらいシーンも多いですよね。
家族からの協力を得つつ、必要であればペットシッターの利用も検討しましょう。とくにトイレ掃除と散歩は、自分以外の誰かに任せるのがベター。
小型犬であっても、突然引っ張られれば転倒のリスクがあり、今まで普通にしていた抱っこも、妊娠した体にとっては負担になることがあります。散歩に行く場合は、基本的には家族にリードを持ってもらい、自分は付き添い程度にしておきましょう。
人獣共通感染症に要注意!母体や赤ちゃんにも危険な病気は?

ここでは、妊婦さんが気をつけたい人獣共通感染症を紹介します。人獣共通感染症とは、人と動物の両方にうつる感染症のこと。犬から人に感染する病気も人獣共通感染症に含まれます。危険な感染症について学び、必要以上に警戒するのではなく、上手に対策することで愛犬と安心して暮らせる環境づくりにつなげましょう。
犬からは感染しないけれど注意が必要【トキソプラズマ症】
トキソプラズマ症は、妊婦さんが危険視するべき人獣共通感染症の一つ。猫の糞から感染する可能性があり、妊婦さんが罹患した場合は約30%の確率で胎児にも感染します。
胎児が先天性トキソプラズマ症を発症した場合、流産や死産を引き起こすことも。感染時は食欲不振や軽い風邪のような症状が特徴で、重症化することで呼吸困難や嘔吐などが現れる場合もあります。
猫とは異なり、犬の糞から、人にトキソプラズマが感染することはありません。しかし、猫の糞が、外の土などに潜んでいる可能性があります。
犬が散歩中に土を掘るなどをして、犬の体に土と一緒に猫の糞が付着して飼主に感染する可能性は、理論上はゼロではありません。しかし、それ以上に
・庭いじりや土いじりを控える(猫の糞が混ざっている可能性があるため)
・生肉を食べることを控える(牛などの家畜もトキソプラズマに感染し、感染した動物の肉を生で食べると人も感染するため)
という点に気をつけて過ごしましょう。
参考:ライオン歯科衛生研究所「【産科医監修】妊婦さんが気を付けたい感染症『トキソプラズマ症』」
日常的に犬に手などを舐めさせているなら要注意【パスツレラ症】
パスツレラ症は、犬に咬まれたり舐められたりすることで感染する感染症です。多くの犬や猫がもともと持っている口腔内の菌が感染の原因で、皮膚症状や呼吸器感染症を引き起こします。
まれに敗血症や骨髄炎などの重篤な症状が現れるケースもあります。とくに愛犬とのキスの習慣がある人は要注意です。
脱水や子宮収縮などの症状も【サルモネラ症】
サルモネラ症の原因となるサルモネラという細菌は、犬などの感染した動物の腸内に存在し、糞と一緒に外に排泄されます。通常、犬は感染しても無症状なので、愛犬が感染していても飼主は気づけません。
人へは、犬との接触(ふれる・キスなど)など、なんらかの形で犬の糞が口に入ることによって感染します。症状は急性胃腸炎が一般的で、妊婦はもちろん新生児にも感染リスクがあります。
とくに小児では、敗血症・骨膜炎・意識障害・痙攣など重症化しやすい傾向に。妊婦さんが感染することで、激しい下痢によって脱水や子宮収縮を引き起こす可能性があります。
参考:elevit『妊婦は生卵は控えてサルモネラ菌が及ぼす影響とは?』
参考:Zoonosis協会『カメ、イヌ等からサルモネラ(胃腸炎)が感染する!?』
早産や低体重児のリスクが上がる【歯周病】
愛犬が歯周病を患っている場合、接触によって人間も感染してしまいます。妊娠中の女性にとって、歯周病は深刻な病気です。歯周病に罹患した妊婦さんは、早産や低体重児のリスクが7倍も高まってしまうといわれています。
自治体が妊婦に歯科検診を勧める理由の一つが、歯周病のチェック。とくに妊娠中は唾液の分泌量が減少するため、口内トラブルが発生・進行しやすい状態です。
参考:おろしまち歯科医院「飼っている犬から歯周病はうつるの❓」
参考:清水歯科クリニック 歯周病・インプラントセンター「妊娠・妊婦と歯周病」
赤ちゃんが生まれたら、犬との生活はどう変わる?

ここでは、出産による愛犬との生活の変化について紹介します。出産直後は、気持ちも体も余裕がなくなるもの。赤ちゃんの安全を優先するあまり、愛犬への対応が後回しになってしまうこともあるでしょう。
人とペット全員が幸せな生活を送るためにも、家族で協力しながらライフスタイルを模索していきましょう。
今まで以上に衛生面を徹底しよう
赤ちゃんの免疫力は万全ではありません。出産後は、今まで以上に衛生的な環境づくりを徹底するように努めましょう。犬のお世話後はしっかり手を洗い、寝具やタオルも別々に保管してください。
犬がふれた物や舐めた者は、赤ちゃんに近づけないように。自分が気をつけるだけではなく、家族にもルールを共有して守ってもらいましょう。赤ちゃんと犬のふれ合いは、生後3~4ヶ月頃から段階的におこなうのが望ましいとされています。
参考:まなべび「【獣医師監修】犬と赤ちゃんは一緒に暮らせる?安全に過ごすためのガイド」
赤ちゃんが優先になるからこそ…愛犬とのコミュニケーションも大切に
妊娠中や産後直後は、とにかく余裕がなくなります。愛犬とのコミュニケーションが後回しになりやすい時期です。自分以外の家族に散歩や遊びなどを担当してもらえるように、あらかじめ話し合っておきましょう。
突然の体調不良の可能性も加味したうえで、ペットホテルや親戚・友人・ペットシッターなどの選択肢も検討しておくと安心です。家族が増えることは、犬にとっても大きな変化です。心をケアして、犬に赤ちゃんの存在を受け入れてもらえるような環境づくりを心がけましょう。
赤ちゃんに近づいても叱らない
新しい家族が増えたことで、犬は困惑や興奮の感情を抱きます。自分の生活が変わる理由が分からず、赤ちゃんに攻撃的になったり、好奇心からベッドに近づいたりすることもあるでしょう。
もし愛犬が赤ちゃんに興味を持って近づいても、大きな声で叱らないように努めましょう。愛犬は、変化する生活に順応しようと頑張ってくれている最中です。
友好的に接しようとしてくれていること自体を前向きに捉え、優しいコミュニケーションを心がけてください。犬が届く範囲や高さに赤ちゃんを寝かせないことも大切です。
出産前から『赤ちゃんがいる暮らし』をシミュレーションしよう

出産というライフスタイルの大きな変化に備え、妊娠中から『赤ちゃんがいる生活のシミュレーション』を始めましょう。方法の例としては、以下のようなものがあげられます。
- ベビーベッドのスペースを決めて早めに設置する
- 赤ちゃんの声を映像や音声で聞かせる
- 普段のお世話役以外の人もお世話に参加する
- 出産後を想定したライフスタイル・スケジュールで過ごす
産後入院中は、赤ちゃんが使ったおむつやタオルなどを持ち帰り、臭いに慣れさせるのも良いでしょう。赤ちゃんを家に迎える際に、環境の変化のギャップをできる限り少なくするように努めてください。
赤ちゃんとの新しい生活。愛犬のメンタルケアも大切に

今回は、妊婦さんと愛犬との暮らしで気をつけたいポイントや、出産後の暮らしの変化について紹介しました。
妊娠中の愛犬のお世話は、無理をしないことが何より大切。家族や周囲のサポートを借りながら、安全な生活を心がけてください。
愛犬のメンタルをケアするためにも、家族の協力が求められます。環境の変化によってストレスが溜まると、問題行動に発展してしまう場合もあります。ペットを含む家族がみんな幸せに過ごせるように、役割を分担して取り組んでいきましょう。













